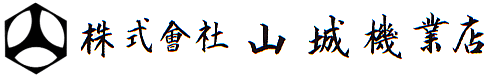 |
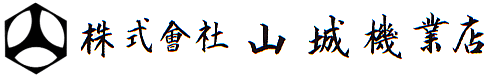 |
|
|
||||||||||||
| 当社は色々な織物を作っていますが、その中でも代表的な品種がこの唐織です。 ここでは、唐織についての説明と当社の織物の特徴をお話したいと思います。 |
||||||||||||
| 「唐織」(からおり)という名前の由来 唐織物、唐織とは、元々中国から渡来した織物の総称でしたが、何時の頃からか、能装束のある特定の織りかたの物を指してそう呼ばれるようになりました。 その理由に付いては諸説がありますが、おそらく、平安時代に発展した有職織物の浮文の綾を、唐織と呼んだことに関連があると思われます。 もともと、織物の技術は、中国を通してもたらされたものですが、その後、もっとも日本的に発展した織物に対して、唐織という名称が残っているのも面白いことです。
二倍織物、二重織物(ふたえおりもの)と呼ばれる。 唐織の織法の基と思われる。 |
||||||||||||
唐織の組織(織物の構造) 生地は三枚綾組織を用い、緯糸(よこいと)ニ越の間に、絵緯糸(えぬきいと)一越を挟み込むように織っていきます。この時、撚りの少ない、大変太い絵緯糸(えぬきいと)を、刺繍のように浮かせて絵文様を織り出します。 絵緯は、文様に応じて、必要な色糸を縫い取るように織り込むので、杼(ひ)の数は 文様の色数以上に必要です。この杼を文様に応じて一つ一つ、経糸(たていと)にくぐらせ、次に地の緯糸(よこいと)を通して、初めて一越が出来上がり、織り進みます。 この時、地経糸(じたていと)の密度が高いほど、絵緯糸(えぬきいと)がしっかりと締め付けられ、織りこんだ糸がほどけません。当社の唐織は、1㎝間に30回、緯糸(よこいと)が通っています。
「ひ」と「わく」 |
||||||||||||
唐織という織物は、生地の密度が高いので薄く仕上がる為、絵緯糸は、織り巾いっぱいに通さず、できるだけ文様の部分だけ往復させます。これは、「縫い分ける」といいますが、コストの許す限りできるだけ細かく縫い分けたほうが、製品としては軽く、また、絵緯糸の抜けにくい、上質な織物といえます。 しかし、これは表面の絵柄が同じものでも、縫い分けがされているか否かで、価格的に大きな違いが出てきます。あまり細かすぎても問題です。 当社の場合、長年の経験から、品質(糸のほつれ、製品重量等)とコストの関係を考え、良心的な物創りを心がけています。
それにより、生地の締まった独特の風合いがでるのですが、反面、これは、当時の撚糸技術が稚拙(ちせつ)であったために、精練した絹糸を、経糸(たていと)として使えなかったという理由があり、織物にサシやスレと呼ばれる、キズが生じやすいという欠点もありました。 当社では精練した糸を生地に使用し、帯という用途に適した、しなやかで軽い生地に仕上がっています。 |
||||||||||||
能装束にみる唐織 世阿弥によって、猿樂から能という演劇に完成された頃は、まだ役柄による装束の規制はありませんでした。それは、国内の染織技術が未発達で、舶来品に頼った高価な衣裳で、数も限られたものしかなかったことにもよります。 装束が、現在見られるような形式になったのは、江戸幕府が、能を式樂としてからのことです。それには、応仁の乱以降、急速に発展した、国内の染織工芸の隆盛による要因も大きく影響しました。 世阿弥時代の装束は、現代には全く残っていませんので、式樂能として形式化されて以降の装束を簡単に分類すると、次ぎのようになります。 大袖もの(広巾もの) 直衣(のうし) --------- 能装束中、最も高貴な役柄をあらわす 狩衣(かりぎぬ)-------- 貴人や公家の男役が用いる。翁用は蜀江文様の錦 法被(はっぴ) --------- 武人のかっちゅう甲冑姿(かっちゅう)や鬼畜が本性を現す場面に用いる 側次(そばつぎ)------- 武人の軍装や唐人の役に用いられる 水衣(みずころも)------ 僧あるいわは庶民のやつれた姿を現す 長絹(ちょうけん)------- 公達武将が単法被(ひとえはっぴ)の代わりに使用する 舞衣(まいぎぬ)-------- 女役の舞の場面に用いる 直垂(ひたたれ)-------- 現実の武士の服装を転用したもので、四、五番目のワキが着る
|
||||||||||||
小袖もの(詰袖もの) 唐織(からおり)------三番目 鬘物(かづらもの)の女役が、表着に着用する。能装束中、最も華麗な 衣裳。 紅色の有無によって、紅入り(いろいり)、紅無し(いろなし)と呼ばれ 前者は、若役、後者は 老役が用いる。 縫箔(ぬいはく)------女役の小袖物として、唐織に並んで重きをなす。刺繍と、すりはく摺箔で模様を あらわす技法からこう呼ぶ。 摺箔(すりはく)------女役の着附に使用する。これも、技法がそのまま装束の呼び名になった。 厚板(あついた)-----男役の着附に使用する。これも、織物の技法上の固有名詞が、そのまま 装束名になった 熨斗目(のしめ)-----能装束としては最も軽いもので、ワキ、ツレなどの着附に、主として用いる。 大口(おおぐち)-----後ろを板のように堅く張らせる、能独特の袴。
|
||||||||||||
唐織に見られる文様について 女役に使われる唐織、縫箔、摺箔などに見られる文様は、他の衣装に使われるものに比べて非常に和様の典雅なものです。 それに対して、男役の衣装である、狩衣(かりぎぬ)、法被(はっぴ)、あるいは厚板などは、強くいかめしい文様類を多く使い、名物裂系の図柄をよく用いられます。 その他には、直衣(のうし)、などに、有職文様が見られます。 このように、主に、明から伝来した大陸系の文様を男役の衣装に、そして、平安朝以来の和様の文様が女役の衣装にと使い分けられていることは興味深いことです。 それらは、四季の変化に富んだ、日本の自然に育まれた、日本独自の文化であり、花鳥風月のような、自然の物や、現象を、取り上げようとする指向は、文様にとどまらず、色名に、その植物や、染色材料そのものの名前を付けている事からも伺えます。 当社で、織り上げています唐織は、もちろん過去の遺産の復元でもありますが、それに留まらず、古今東西、あらゆる意匠を参考にして、唐織という織法を生かせる、現在の文様を作ることに努力しています。
|
||||||||||||
| 唐織には、自然の草花、しかも秋の花が多く取り上げられ、それは、王朝の美意識につながるものです。 | ||||||||||||
能装束の色 現在残されている能装束は、かなり退色していますが、それを、作られた当時の色に復元してみると、まず、その鮮やかで、多彩なことに驚かせます。 このことは、当時の技術から考えて、非常に贅沢に、高価な染料をふんだんに使ったものであることがわかります。 それは、上流社会における染色と、一般的染色、特に地方における染色とが、大きく区別されていたことにもよります。 すなわち、上流社会では、できるだけ純粋に、染料として使用し、最も高い明度に向かって染め上げたのに対して、一般では、とうてい贅沢に使用することができなかった為に、他の含有成分も、多く含まざるを得なかったという、事情によります。 また、これを、世阿弥の言葉で言うと、「幽玄、すなわち、花」つまり、華やかで、きらびやかな表象としての色と、考えることができます。 しかし、私どもが最も驚かされることは、50年100年先に退色した色を想定して、配色がなされていたという事実です。これは、織り上がったばかりのときには、やはり、生々しくて、地と文様との間に、なじみができていません。従って、能の世界では、一退色、ニ退色等といい、一退色は50年とされ、製織された装束は、まず、仕舞い込まれて、程よく落ち着き、なじむのを待って、使用されたといいます。 当社では、これらのことを、良くふまえた上で、過去の作品を参考にし、現在の溢れかえる色の中から、慎重に、新しい色を探し出し、今の時代の唐織を創り出そうと、日夜研鑚しています。 |
||||||||||||
| このページのトップに戻る |
||||||||||||
|
|
||||||||||||